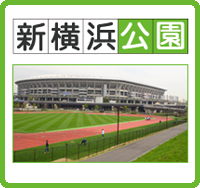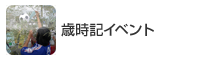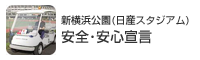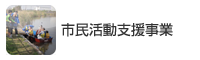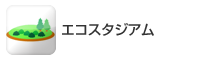★ 写真 アカバナユウゲショウ(アカバナ科マツヨイグサ属)が咲いています。
撮影日時: 平成20年度5月16日
場 所: 新横浜公園北側園地
アカバナユウゲショウ(アカバナ科マツヨイグサ属、多年草)が淡紅色の花を咲かせています。「赤花夕化粧」なんて、なんと風雅な名前でしょう。名前からのイメージだと純国産かと思いきや南アメリカ産の帰化植物だそうです。そう言われれば、茎もピンと伸びているし、花も大きく派手です。
この時期北側園地は菜の花の黄色から、クローバーやハルジオンorヒメジョオンの白い色に変わり、赤い花は遠目にも目立ちます。
アカバナユウゲショウはマツヨイグサの仲間で、マツヨイグサはその名のとおり、夕方から花を咲かせます。ユウゲショウの名もそれに由来します。ところが、日本ではユウゲショウはオシロイバナの別名でもあり、それと混同しないためにアカバナを前に付けたのでアカバナユウゲショウとなったとのことです。そう言われれば北側園地のアカバナユウゲショウは昼間から花を咲かしています。ひょっとしたら新品種かと思いましたが、そうではなくアカバナユウゲショウは昼間から咲く性質を持っているとのことでした。
それと、アカバナなのに白い花もあるようなのでご注意を。
前回の新横浜公園生き物観察日記(21)はこちら
5月28日から30日まで横浜ではアフリカ開発会議(TICAD)が開催されています。
今、横浜市は様々な場所でアフリカ関連のイベントが開催されアフリカンムードでいっぱいです。
日産スタジアムでも先日24日も「RUN FOR AFRICAリレーマラソン」というマラソン世界記録を持っているエチオピアのゲブラセラシエ選手の記録に挑戦というイベントが開催されました!
日産スタジアムで何かアフリカ関連のモノがないか探してみましたが、スタジアムツアーで見ることができるロッカールームは南米のブラジルだし、コンコースに貼られている大型写真も違うし・・・。しかし、スタジアム中を探し、ありました!!!
スタジアムショップに!
「スタジアムショップはマリノスグッズがメインだし、アフリカとどうつながっているんだ??」と思われるかもしれませんが、ショップ入口の上の壁を見てみてください!
そう2002年のワールドカップの出場国が描かれている世界地図にありました。
アフリカ大陸です。
2010年のワールドカップ開催国の南アフリカもありました。
ちなみに6月2日は2010FIFAワールドカップ南アフリカアジア3次予選が日産スタジアムで行われます。
スタジアムショップにお越しの際は入口の上にあるワールドカップ出場国地図を見てみてくださいね
みなさんこんにちは。
小学生から大人まで5段階にコースを分けて、各グレードのカリキュラムに基づいた陸上競技の教室を開催している日産スタジアム・アスレティクスアカデミー(NSAA)に、体験コースがあるのをご存知でしょうか。
今回、グレード5の健康コース サクセスフル・エイジング系のコースを体験しました。
普段、運動不足の私が練習についていけるか不安でしたが、一生懸命走り、とても気持ちの良い汗をかきました。
「走る」ことが好きになる、大満足の体験コースでした。
一流の先生方のすばらしい指導がありますよ。
本当に魅力ある素晴らしい体験ができました。
是非みなさまも体験コースを通じてNSAAのすばらしさをご体感ください。
お待ちしています。
NSAAのホームページはこちら!
★ 写真 ベニバナトチノキ(トチノキ科)が赤い花を咲かせています。
撮影日時: 平成20年度5月8日
場 所: 新横浜公園東ゲート緑地
トチノキは大きくなる木です。この時期天狗の団扇(うちわ)のような大きな葉と白い花を咲かせます。でも、今、日産スタジアムで咲いているトチノキは赤い花を咲かせています。この種はベニバナトチノキといって、マロニエ(セイヨウトチノキ)と米国産のアカバナトチノキの交配種です。赤い花の珍しさからか街路樹や公園樹として多く使われています。
トチノキと言うより「マロニエ」と言った方が馴染みがあるでしょうか。マロニエと言えばフランスのパリ。パリの初夏と言えば自転車競技の「ツール・ド・フランス」。今から十何年前のことでしょうか、NHKのサンデースポーツの番組だったと思いますがツール・ド・フランスを放映していて、その映像に度肝を抜かれたことがあります。自転車競技といえば競輪しか知らなくて、ロードの競技なんか初めてですから、200名、もっとかな?もの選手が一団となってパリ市外を走り抜ける。その迫力に圧倒されたことが思い出されます。空撮の映像では街路樹の枝越しにカラフルなユニホームの一団が見え、その街路樹に白い花が咲いているのを見たような記憶があります。あれはマロニエの花だったのでしょうか。昔のことで定かではありませんが。
ベニバナトチノキは普及して間がないのでそれほど大きな木を見ることはありません。
事実、新横浜公園の木もまだ小さく目立ちませんが5年、10年経てば見上げるような姿を見せてくれるでしょう。楽しみです。
前回の新横浜公園生き物観察日記(20)はこちら
★ 写真 ヒトツバタゴ(モクセイ科)が白い花を咲かせています。
撮影日時: 平成20年度4月28日
場 所: 新横浜公園東ゲート緑地
新横浜公園は以前、田んぼや畑であったものを遊水地兼用の運動公園として整備したものです。ですから、今ある樹木は整備工事で植栽されたものです。工事で植栽される樹木は剪定、病害虫に強く、手入れしやすく、安価なものが好まれます。そうすると、公園に植栽される樹種は限られたものになりがちで新横浜公園の植栽もその例に洩れません。しかし、中には珍しいものもあります。ヒトツバタゴもそのひとつです。ヒトツバタゴの名の由来は、一つ葉のタゴ(トネリコ)からきたもので、トネリコは複葉なのにこの木は単葉だったので「ヒトツバタゴ」になったとのことです。花が咲くその姿は雪が積もっているように見えることから学名:Chionanthus retususも雪(chion)と花(anthos)に由来します。山が緑濃くなるこの時期に白い花を咲かすヒトツバタゴは遠目からも目立ちます。また、この木はその生息分布にも特徴があり、本州中部木曽川流域と対馬に分かれて生息しているので隔離分布と呼ばれます。それにしてもなぜ、公園設計をした人はこの木を選んだのでしょうか。きっと信州あたりの人で、子供の頃、ヒトツバタゴの花を見て育ち、故郷の山が懐かしくなったのかも知れません。
それと蛇足ですが、環境省のレッドデータブックの絶滅危惧種?類でもあります。
前回の新横浜公園生き物観察日記(19)はこちら
ゴールデンウィーク中、日産スタジアムでは様々なイベントが行われ、沢山の人々にお越しいただきました。
5月4日・5日に、しんよこフットボールパークにてキャノンカップ2008が行われました。子供たちの一生懸命なプレーにお母さん、お父さんも熱い声援を送られていました!
5日はJA全農チビリンピックも開催。陸上・サッカー・卓球の競技に子どもたちが参加し、特別ゲストの方々も一緒に競技に参加され、スタジアム中に皆さんの元気な声が響き渡っていました。この参加者の中から未来のオリンピック選手がうまれるかも!
フリーマーケットも沢山の方々で大賑わい。掘り出し物をゲット出来ましたか?次回フリマは5月11日(日)、6月15日(日)開催予定です。ぜひお越しください。
6日は横浜F・マリノス応援ツアーでは試合直前のマリノスロッカーやピッチ・特別観覧席をご覧いただきました。普段は入れない所を見れて、みなさん大興奮!
4月12日から皆様に折って頂いていた千羽鶴をマリノスさんに届けました!試合の結果は引き分けでしたが、千羽鶴の力はきっと次回に伝わるはずです。
このように日産スタジアムではこれからも様々なイベントが行われます。
詳細は日産スタジアムホームページでご確認ください!
みなさん、こんにちは。
お待たせしました。「芝生観察日記」の第六稿です。
3月のJリーグ開幕戦から約2ヶ月のご無沙汰となってしまいました。
この間、日産スタジアムも職員の異動や事務所内の引越しがあったりで、この芝生観察日記も慌しさに埋もれて遠のいてしまいました。しかし、この間も芝生は元気でしたよ。
写真1は、3月の開幕戦で傷付いた部分に、夏芝が伸びて傷口が埋ってきた状況です。2月の気温が例年よりも低めだったためやや出遅れた夏芝でしたが、今では例年を上回る勢いで、冬芝から夏芝への切り替えが進んでいます。
写真1
しかし、ただ一点、懸念されるのは例年よりも冬芝の芽数が多く、元気なため夏芝が出るのを邪魔しているのです。この状況に対する対策として、芽数を調整するため既にサッチングやグルーミングといった切り替えのための作業を行っていますが、これらの作業についてはまた別の機会に説明します。
写真2は、4月末に撮ったフィールドの全景です。冬芝の芽数が多いため色合いも濃く、綺麗なゼブラ模様となっています。
写真2
現在、芝生の刈高は20mm(5月3日時点)。6日にJリーグがあるための設定ですが、この試合が終わるとしばらくフィールドの利用がないため、切り替えのための低刈りとして15mmまで下げる予定です。
ちなみにJリーグなどのトップレベルの平均的な芝生の刈高は、20?25mmです。これは、スタジアムごとの芝生の種類や時季によっても多少前後します。
我々が夏芝と冬芝の切替わり状況を示す時、5対5とか6対4といった表現をしますが、現状は1対9。夏芝が1に対して冬芝が9といった感じでしょうか?
今後は5月末で4対6、6月末には逆転して6対4、7月末で7対3という目処で切替わりが進み、最終的に全部夏芝となるのは8月末から9月に入ってというペースですが、これはあくまでも理想であり、冷夏だったりすると冬芝が完全に消えず、再び冬芝の播種を行う季節を迎えることもあり、毎年お天気と相談しながらの作業となります。
芝生の割合が変化すると芝生の色合いも必然的に変化していくので、その辺もお楽しみに。
さて、今年の切り替えはどうなる事やら??途中経過はみなさんにも随時報告していきますので、次回もお楽しみに!!
前回の芝生観察日記(5)はこちら