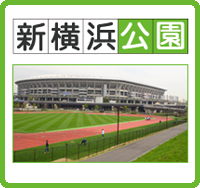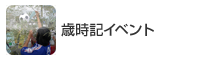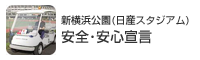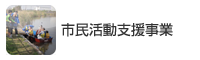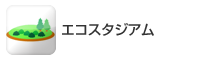12月20日(日)
恒例となった「もちつき&しめ縄飾りづくりが」行われました。 47名の参加者(小学生以上1人1000円)で実施されたこのイベントは、日産スタジアムと運営ボランティアさんの共催で行われました。
今年もボランティアさんが、事前の準備から当日の運営まで、大活躍!
「もちつき」はもちろん、内容は盛りだくさん
(1)スタジアムミニツアーでは、タイムリーにFIFAクラブワールドカップUAE2009で優勝をしたFCバルセロナが2006年に使用したロッカーにタイムスリップ 普段は行けない場所を探検し?
 ツアーはわくわく…ドキドキ
ツアーはわくわく…ドキドキ
(2)蒸篭(せいろ)でふかした餅米をほおばったら… お口の中でお餅になって…
 蒸かしたてのお米は最高
蒸かしたてのお米は最高
(3)自分の力で、お餅をついて…
 そ?れっ気持ちをこめて
そ?れっ気持ちをこめて
(4)食べるお餅は、自分でからめて…
 お餅の感触はいかが?
お餅の感触はいかが?
(5)お腹いっぱい…心もいっぱい?
 いただきま?す
いただきま?す
(6)昔遊び(こま回し・ケン玉・めんこ・竹とんぼなど・・・)を楽しんで、陸上トラックを走り回り…
 飛べ!竹とんぼ!
飛べ!竹とんぼ!
(7)(8)大人も子どもも「注連縄(しめなわ)」づくり 子どもたちは藁の感触を楽しみ 大人は縄を編むところからはじめます
 子ども注連縄教室
子ども注連縄教室
 大人もゆっくり注連づくり
大人もゆっくり注連づくり
(9)みごと完成!ご覧ください!
 最高の笑顔を ありがとう!
最高の笑顔を ありがとう!
という感じで、あっという間の半日を過ごしました。
皆様 お疲れ様でした。良いお年をお迎えください!
小机小学校の児童達がサクラソウの植わっている場所の手入れをしてくれました。
このサクラソウは、今回手入れをしてくれた6年生が5年生の時に学校で育て、今年6月に
新横浜公園に植えてくれたものです。
植えてから半年たち、サクラソウの植え替え時期も来たので、サクラソウの生育状況の確認
とサクラソウの芽吹きを助けるために枯れ草を刈り取ってくれました。
生育状況は横浜さくらそう会の三宅さんに見てもらいました。三宅さんは「地植え」(畑に直
接植えることの意)は初めてなので、と言いながらも大丈夫と仰っていました。
サクラソウの手入れ(草刈)は天候不良で順延を重ね今回が3回目です。朝は曇りがちの
冷たい天気でしたが、午後になると薄日のさす天気となり、新横浜公園北側園地は100名
を越す児童達の歓声で賑わいました。
作業は靴をぬらし、泥んこに、なりながら頑張って、きれいに片付けました。
皆の頑張りにサクラソウもきっと応えて、きれいな花を沢山咲かせてくれると思います。
来年の楽しみがまた一つ増えました。


↑ サクラソウ植栽地の草刈風景。 ↑ 枯れ草も無くなりスッキリしました。
なれない作業ですが、皆、一生懸命です。 「サクラソウは太陽の光と水が大好き」と
は、さくらそう会の三宅さんの言葉です。
午後の陽射しが地面を暖めます。
 今、日産スタジアムおよび新横浜公園一帯で、数々の「クイズ」が出題されています。
今、日産スタジアムおよび新横浜公園一帯で、数々の「クイズ」が出題されています。
ご来場のみなさまは、お気づきになりましたか??
 スタジアム初のイベント、「クリスマス スペシャル クイズラリー」も、残すところあと1週間となりました!まだ参加されていない方は、公園内のクイズの中から3つ選んで解答し、クイズラリー専用の応募用紙でご応募ください。
スタジアム初のイベント、「クリスマス スペシャル クイズラリー」も、残すところあと1週間となりました!まだ参加されていない方は、公園内のクイズの中から3つ選んで解答し、クイズラリー専用の応募用紙でご応募ください。
![]() お一人様1枚限り有効、参加は無料。
お一人様1枚限り有効、参加は無料。
正解者の中から抽選で、スタジアムにちなんだ素敵なプレゼントがあたります!
ご応募いただいた際の「控え」は無くさないでくださいね。
●イベントの概要:http://www.nissan-stadium.jp/enterprise/xmas2009.php
![]() 広大な新横浜公園ならではのこの企画。応募用紙の裏面にある地図を頼りに、自由に散策してみてください。
広大な新横浜公園ならではのこの企画。応募用紙の裏面にある地図を頼りに、自由に散策してみてください。
ホームページでもご紹介をしている、様々な種類のスポーツ施設を覗いてみるもよし、便利なショップやくつろぎのレストランを利用するもよし、自分だけのお気に入りの場所や絶景ポイントを探してみるもよし。
自然豊かな園内を元気に散歩すると、12月の寒さも吹き飛ぶステキな発見があるかもしれません。常連のお客様も初めてご来場される方も、このイベントがきっかけとなり、皆様とスタジアムとの新たな接点が生まれれば幸いです。
![]() 応募の締め切りはもうすぐです(2009年12月25日まで)。
応募の締め切りはもうすぐです(2009年12月25日まで)。
ここで、ブログをお読みの皆様へ特別に、出題箇所の大ヒントを出したいと思います!

その(1) ボール1つあれば無料で楽しめる広場。 日産フィールド小机側の入り口から階段を下りると・・・。

その(2) スタジアムから足を伸ばし、 迫力満点の投球が見られるここで、 クイズに挑戦。

その(3) 第二駐車場の近く。 お隣では、少年野球やソフトボール、 少年サッカーも開催されます。
![]() 応募用紙の配布場所は、第二レストハウス・しんよこフットボールパーク・日産ウォーターパーク・レストランMoi(モア)・Lap Time(ラップタイム)・スタジアム管理事務所などです。
応募用紙の配布場所は、第二レストハウス・しんよこフットボールパーク・日産ウォーターパーク・レストランMoi(モア)・Lap Time(ラップタイム)・スタジアム管理事務所などです。
http://www.nissan-stadium.jp/enterprise/pdf/xmas200902.pdf
![]() 新横浜公園・日産スタジアムへのご意見も、忘れずにご記入お願いします。
新横浜公園・日産スタジアムへのご意見も、忘れずにご記入お願いします。
興味のあるスポーツ、参加してみたいイベントのアイディア、スタジアムでかなえたい夢などこっそり教えてください。ご応募お待ちしております。

★ 写真 キノコ(オオシロカラカサタケ)です。見た目きれいですが毒です。
撮影日時: 平成21年12月4日
場 所: 北側園地減勢地側植栽地
北側園地を自転車で巡回していると、草むらにコンビニのビニール袋が捨ててあるのが目に付きました。拾おうと手を伸ばすとビニールの感触ではありません。白いキノコです。
笠の大きさは15cmほどもあります。でも、キノコの名前が分かりません。図鑑を調べましたが私の手持ちの図鑑には載っていません。そこで、鶴見川の流域センターに問い 合わせたところ「オオシロカラカサタケ」の名を教えていただきました。ハラタケ科ハラタケ目のキノコで、熱帯、亜熱帯に生息するキノコ、それも毒キノコだそうです。以前、 港北区の綱島で見つかり話題になったそうです。
オオシロカラカサタケはキノコの仲間としては乾燥に強く、公園の芝生や草地で目にする事が多いそうですが、施設園芸(温室やビニールハウス内で植物の栽培を行うこと)方 面では以前から作物に害を与えるキノコとして知られており、予防マニュアルもあるそうです。外来種は新横浜公園内に沢山いますが、キノコまで外来とは驚きです。南方系のキ ノコがいくら温暖化とは言えこんなところまで北上して来るとは、でもこのキノコ1週間も待たず消えてしまいます。消えると言えば「光陰矢のごとし」の例えどおり時も消えて 今年も後わずかです。では、良いお年を。

★ 写真 コサギです。
撮影日時: 平成21年11月27日
場 所: 北側園地保護区
コサギです。餌を探して水の中を足で探っています。
コサギはサギ科シラサギ属の留鳥で白鷺の中では一番馴染みのある鳥です。シラサギはその体の大きさでダイ(大)、チュウ(中)ショウ(小)と分けられ、一番小さいからコサギ(小鷺)です。分かりやすい分け方のようですが、屋外で遠目で見ると案外と分かりません。大と小は分かり易いのですが、中と小は見分けが難しいように思います。コサギ(小)に近いチュウサギ(中)もいれば、チュウサギに近いコサギもいると言うことでしょうか。
もっともシラサギと呼ばれるものは、この3種だけでなく冬羽のアマサギもそう呼ばれています。白いサギなら、皆、シラサギです。なかでもコサギは新横浜公園でもよく見る事ができますが、数が多いわけではありません。群れた姿も見た事がありません。鷺山と呼ばれるコロニーを作る習性の割に行動は個別的で、採餌方法も他のサギとは違います。足で池底を探るようにかき回し、獲物を追い出し捕まえます。足技が得意ならサッカーも上手なのではないでしょうか。華麗な足さばきをフィールドでも見てみたいものですね。

★ 写真 ガガイモの実です。
撮影日時: 平成21年11月22日
場 所: 北側園地整備予定地
気温が下がると北側園地のアシやオギも黄葉し葉を落とします。葉を落とした茎に何かぶら下がっています。カラスウリかとよく見ると、実の形が違います。色も薄い緑色で縞もありません。ガガイモの実です。ガガイモ(ガガイモ科ガガイモ属)つる性の多年草です。夏の間はアシの陰に隠れ、目立ちませんが、雑木林の林縁に見かける植物です。
この実は「袋果」と呼ばれ中に綿毛のついた種が入っています。乾燥すると茶色の殻が二つに割れて中の種が風によって飛ばされます。この様を見て、昔の人は神話を編み出しました。古事記や日本書紀に出てくる「スクナヒコナノミコト(小名彦命、須久奈古命)」の話です。ガガイモの殻が神様の乗り物(舟)になるのですから、おどろきです。
スクナヒコナノミコトは小さな神様で(一寸法師の原型との説もあります)海の向こうからガガイモの殻の船に乗って「因幡の白うさぎ」で良く知られたダイコクサマ(大国様、大国主命)のもとに来て大国様の国づくりに協力した神様だそうで医薬、温泉をつかさどる神様でもあります。国づくりが終わると、また「常世国」(桃源郷?)に帰ってしまったそうですが「出雲国風土記」には稲と水田耕作の普及に貢献した神様と書かれているそうです。ガガイモの実(殻)にそんなドラマがあったなんて、知りませんでした。
平成21年11月28日、新横浜公園の3号水路に横浜さくらそう会丹精の苗を植え込みました。
昨年は一芽づつに分けて植え込みましたが、今年は株分けしないで大株のまま植え込みました。
一芽づつに分け、数芽を一緒に一鉢に植え込むのが一般的で、昔からの植栽方法ですが、昨年の経験から屋外での地植えの場合には大株のまま植えたほうが環境への適応や雑草との競合にも強いのではないか、との考えからです。
植える場所も、昨年より広くしました。昨年は夏場の暑さ、冬場の乾燥を考慮して水路際に植えましたが、この場所は地下水位が高く、乾燥の心配はないのが分かったからです。
これからがサクラソウの植え替えのシーズンです。
それにあわせて、新横浜公園のサクラソウ植栽地も広がって行きます。
 |
 |
|
| サクラソウの植え付け風景。 写真左の裸地の部分が植栽の終わった場所です。 |
植え付け前の苗を並べた状況。 白い塊が苗です。一つに3?4芽あります。株が大きいので株間が狭く感じられます。 |
この数を聞いて驚かれたり、疑問に思ったりされる方もおられるかと思いますが、正直言って私もその1人でした。ほんとに、そんなにいるの?
そこで、このヘイケボタルの育ての親、桐蔭学園高校の池谷先生にお聞きしました。なぜ5,700匹と分かるのですか? 先生の答えは明快です「数えたからです」。あんなに小さな幼虫を5,700も数える事が出来るなんて、驚き意外の何者でもありません。
でも、驚くにはあたりません。以前、池谷先生がヘイケボタルのオスメスの発生比率を調査された時には1万数千頭のヘイケボタルの全個体数の調査をされていますから。
放流場所は多目的運動場の東側、1号水路が2号水路と合流する場所です。この水路の底にはコンクリートが打ってあり、水路巾も広く水深も浅い(3?5cm)ので天敵のザリガニが少ないとの判断です。
また、ナイター照明から遠く、公園の中では比較的暗く、成虫になった時ホタルの発光行動の妨げにならないだろうとの思いもあります。
 |
 |
|
| 放流地点の現況 合流点から下流をのぞむ |
放流後の状況 白く見えるのがホタルの食べた後の巻貝の殻で、 写真下側の黒いものがホタルの幼虫です (分かるでしょうか?) |
この保護区には今年春600頭のヘイケボタルの幼虫を放流しましたが発生したのはたったの1頭と言う、惨憺たる結果に終わった場所です。
その原因の一つとして「ザリガニ」の食害があげられ、今回の駆除となりました。
ザリガニの駆除がしやすいように草を刈り手網とスコップで捕獲作業開始。手網で取れるザリガニは小さなものですが、巣穴にもぐっているザリガニは大きくその中の1匹は抱卵していました。2時間の作業でザリガニ(大)7匹(小)92匹、ウシガエルのオタマジャクシ(大)14匹(小)123匹を捕獲しました。その他にはギンヤンマのヤゴ、イトトンボのヤゴ、魚ではカダヤシ、ハゼの一種が捕れました。
 |
| 保護区の現況写真。 1週間前に草刈は終わっていましたが、排水は先日の雨のせいもあってこれが限界です。 |
 |
| ザリガニの捕獲中、巣穴を見つけスコップで掘り下げてゆくと赤い大きなザリガニが見つかります。 自然科学部の生徒たちは冷たい水で泥んこになりながらも捕獲のたびに歓声を上げていました。 |
芝生観察日記の第十五話です。
前回の冬芝播種(オーバーシード)から少し時間が空いてしまいました。追い播きした冬芝の種も今では根を下ろして美しい芝生になっていますが、今年の秋は寒暖の差が激しく、ここぞというタイミングで雨に見舞われる天侯は、芝生にとって決して良好とは言えず、冬芝の種も発芽してから芝生になるまで思うように育ってくれませんでした。
北国からは初雪の便りがあちこちから届き、いよいよ冬の訪れを感じさせる季節となりました。日産スタジアムの芝生もこれから訪れる厳冬期に備えた準備を始めています。夏芝は貯蔵養分を蓄え来春の萌芽に向けて休眠(動物でいう冬眠)が近づいています。夏芝が休眠している間のフィールドを緑に保ってくれる冬芝は着実に根を下ろして株を太らせています。とはいえ、冬芝はまだまだ大人にはなっていません。急激な気温の低下によって葉が萎縮して生育を鈍らせてしまう恐れがあります。
このような寒さによる影響から芝生を守るため一週間ほどビニール製のシートを設置して保温したのですが、期間中の雨が災いして予定よりシートの設置期間が長くなった結果、夏芝に病気が発生してしまいました。正式な病名は「カーブラリア葉枯病」ですが、通称「犬の足跡」と呼ばれています。
 |
 |
その症状から付いた名の由来通り、犬が歩いた足跡のように芝生が赤く枯れてしまいます。通常は高温多湿な季節に発生する病気なので季節外れではありますが、シートを設置したためその環境を作ってしまったようです。スタンドやテレビ画面では判らない程度の病気ですがちょっと想定外でした。
芝生も生き物なので我々が風邪をひくように病気にもかかります。人間社会でも新型インフルエンザが流行っていますので気をつけましょう。