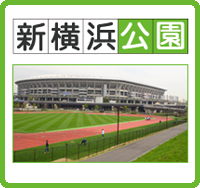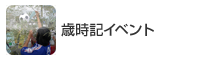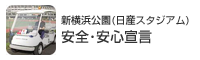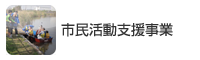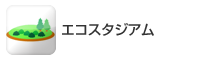★ 写真 オトコエシ(男郎花)です
撮影日時: 平成22年8月19日
場 所: 新横浜公園北側園地
北側園地の植物もこの暑さと乾燥で元気がありません。
でもその中で白い花を咲かせている草があります。「オトコエシ」です。オミナエシ科の多年草です。オミナエシ(女郎花)に対してオトコエシですが当て字にしても「男郎花」をオトコエシとは無理があるように思いますが、どうでしょうか。女郎の意は遊女のことですが、美しい女の意もあるそうです。そうであればいい男の意で「男前」とか「男伊達」をつけて「男前花、男伊達花」をオトコエシと読むのも一興だと思いますが、まあ、どうでもいい話です。忘れてください。
このオトコエシは群馬県昭和村の教育長だった角田さんから頂いたものです。送っていただいたオミナエシの種の中に入っていました。播いて3年目です。
オミナエシは秋の七草のひとつで良く知られていますが、オトコエシの知名度は今一つです。でも、薬草としての薬効(腫れものの解毒)もあり、山菜としても利用できるとのことです。若い芽を天ぷらにしたり、おひたしにしてもおいしいそうです。
夏枯れのこの時期、北側園地ではオトコエシの花は貴重です。白い花の食卓に多くの虫たちが集まっています。結構頼りにされています。

★ 写真 スベリヒユです。暑さに負けない草です
撮影日時: 平成22年8月9日
場 所: 新横浜公園北側園地
スベリヒユ(ナデシコ目スベリヒユ科)南アメリカ原産。畑地雑草の中でも多肉質で乾燥に強く難防除雑草と呼ばれ農家の人からは嫌われています。
でも、その強健さゆえに人の記憶に残っていることがあります。戦後の食糧難の時に食べたことがある、と言う話です。でも、どんな味がしたのでしょうか。
空腹と貧しい食卓に少しでも彩りを添えてくれたのでしょう、でも、感謝の言葉を聞いたことはありません。美味しくなかったのでしょうか。
今は飽食の時代、無理して食べるような物ではないのでしょう。健康に良いという話も聞きません。その代わり「ハナスベリヒユ」と言う花が最近、園芸店の店先をにぎわせています。ハナスベリヒユと言うより「ポーチュラカ」と言う名の方が馴染みがあるかもしれません。同じ科の「マツバボタン」に似ていますが、マツバ(松葉)ボタンは1年草。スベリヒユは多年草(冬越しできればですが、寒さには弱いのです)で栽培も簡単です。花色、花形は、まだ、マツバボタンに一日の長があるように思いますが品種改良が進めば
そのうちきれいな花を咲かせる難防除雑草として北側園地に君臨する時代が来るかもしれません。そんなことになったらどうしましょう、悩みが一つ増えました。

オオミズアオ(チョウ目ヤママユガ科)です。大きな蛾です。サツキツツジの植え込みの中に風を避け
るように止まっていました。
蛾の多くは夜行性で昼間目にすることは少ないのですが羽化したてでしょうか、枝を揺らしても動きま
せん。姿が三角翼のステルス戦闘機にも似ているように思いますが、例えが無粋ですね。
オオミズアオの学名は「Actias artemis」でartemisはギリシャ神話の女神アルテミスに由来します。
アルテミスは月の神で太陽神アポロンの兄弟神でもあります。蛾の多くは夜行性ですから月の神の
名がふさわしいと考えられたのでしょうか。
ところが、最近の研究で(2008年)日本のオオミズアオ(オオミズアオ・本州・九州・対馬亜種)は外国
にあるオオミズアオの基本標本とは違う種であることが分かり学名も「Actias aliena」に変更になった
とのことです。alienaは「他所の、外国」の意味だそうですが、まさか月のことではありませんよね。日本
の蛾ですから月つながりで「かぐや姫」に因んだ名がつくと良いのにと思ったりします。今回の場合、
亜種名が種名に格上げになったということですが、変わらないことが基本の分類の世界も変わるん
ですね。
★ 写真 カマキリ(蟷螂)の子どもです。
撮影日時: 平成22年7月30日
場 所: 日産フィールド小机外周植栽地
カマキリ(カマキリ目カマキリ科の肉食性昆虫)です。今年生まれたのがこんなに大きくなりました。カマキリは日本に2科9種がいますが、これはハラビロカマキリの幼生です。子どもながら獲物を狙う姿にはハンターの凄みがあります。と言うのは嘘でとてもかわいい姿をしています。こんな姿を見ると「蟷螂の斧」の言葉を想い出します。自分の力ではとてもかなわないような敵にたち向かうことの意味ですが、向う見ずなニュアンスが強く、ほめ言葉とは言えないでしょう。でも、この言葉にまつわる故事はそれとは少し違います。カマキリの名誉のために少し書きます。
中国の古代説話集「韓詩外伝」に書かれた故事では、斉の荘公(春秋時代、斉25代目の君主)が狩に向かう途中、荘公の馬車の前に立ちふさがる虫を見つけ、従者に虫の名を尋ねたところ従者が「この虫はカマキリと言い、前に進むことしか知らなく退くことを知りません、自分の力のほどもわきまえず一途に敵に当たる奴です」と進言したところ、荘公は「この虫が人であったら、天下に並びなき勇者となったであろう」と言って馬車を戻させたということです。荘公と言う人は武を尊び配下にも勇敢な武人が多かったそうです。兵の士気を鼓舞する言葉としてカマキリを使ったわけですが、褒められていますよね。
みなさんこんにちは。
新横浜公園の投てき場で開催されているラクロス体験会=「ラクロスパーク」は皆さんご存じですか?
ラクロスという馴染みの浅いスポーツを日産スタジアムで広めていこう!と毎月第4日曜日にラクロスパークを開いています。
今回のラクロスパークは7月25日(日)に開催しました。
今回は、お天気にも恵まれて真夏の中でのラクロスパーク♪
暑さにも負けず、一所懸命ラクロスに打ち込む姿が印象的でした!




今回もたくさんの参加者にご参加いただき大変盛り上がりました。
是非みなさんもラクロスを体験しに日産スタジアムへ足を運んでくださいね。
今回はこんな触れ合いがありました。
初めてきた、Nちゃんとリピーターで来ているRちゃんがラクロスパークで友達になりました。
お互い最初は人見知りでしたが、プログラムを通じてどんどん仲良くなっていきました。
スポーツって言葉なんていらない。互いに触れ合うことでいとも簡単に友達になれたりできるんだな、と見ていてとてもほほえましかったです。
「ラクロス」というスポーツの起源は、ボールを命に見立てて何万キロも離れたゴールまで運ぶという、繋げるスポーツだったようです。
繋げるスポーツによって繋がっていく人と人。
みなさんも是非ラクロスを体験しながら新しい出会いや、友達との絆、親子の絆をさらに深めてみてはいかがでしょうか?
朝10時よりプログラムが始まりますのでぜひ遊びにいらしてください♪
次回は8月29日(日)です。
10:00?12:00 ラクロス体験会(どなたでも参加できます)
参加費 一人500円
ラクロスパークのブログはこちらから↓
http://blog.goo.ne.jp/lacrosse_communications_japan
ご参加お待ちしております☆
新横浜公園のヘイケボタルの発生状況報告です。
平成22年7月31日(土)午後8時45分発生を確認しました。発光を確認できたのは3頭です。場所は1号水路と2号の合流点右岸側のアシの草むらの根元です。
昼間は気温が上がり、8時過ぎても蒸し暑く、風もなくホタル発生には好条件となりましが3頭以上の発光を見ることはできませんでした。しばらく見ていましたが明滅するだけで動きません。飛ぶ姿を見たかったのですが叶いませんでした。
今回の調査は横浜ほたるの会の観察会でもあります。6月13日に新羽中学校自然科学部の生徒が幼虫を放流した田んぼから調査を開始しましたが、テニスコートの照明と、堤防上の照明で田んぼも明るく、ここでホタルの姿を見ることはできませんでした。事前調査でこの場所にホタルが出ていないのは分かっていましたから、ショックはありませんでしたが、ホタルに関してはベテランの方々もその理由を計りかねていました。
放流した幼虫は健康な終齢幼虫。放流場所も出来たばかりの新しい田んぼで天敵のザリガニはいません。水質も問題ないとなると、上陸場所の土質、形態と言うことになりますが、現在の段階では確認しようがありません。公園照明の明るさは問題ですが、これも推測の域を出ません。発生時間が遅いのは事実としてあるので影響はあると考えられますが、それが発生を抑制しているかとなると確証はありません。ホタルが成虫になった後、光りを避けて逃げてゆくことはあるかと思います。強い光に向かってゆくとの説もありますが、もし、そうだとしてもどこに行くのでしょうか?
屋外にホタルの発生地を復元するということは、室内での100%の飼育技術をもってしてもそんなに簡単ではないということでしょうか、一般的には放流数の1割が発生数の目安と言われているのですが。 「ヘイケボタルの里づくり」の試行錯誤はこれからも続きます。

↑ 調査風景。1頭でもいれば元気になれるのですが残念です
★ 写真 イラガの幼虫です。幹に2匹いますが下の方は繭をつくり始めています。こ
の暑い中、越冬の準備でしょうか? 幼虫の周りに脱皮後の繭が見えます
撮影日時: 平成22年7月30日
場 所: 第一レストハウス横の植樹帯
ヒロヘリアオイラガ(チョウ目イラガ科)の幼虫です。日本に27種類くらいのイラガがいると言われていますが、このイラガは新参者、簡単に言えば外来種です。原産地は東南アジアから中国南部で1920年ころに鹿児島県で確認され、その後、日本を北上し1990年から2000年の間に神奈川、東京まで生息範囲を広げているとのことです。
普通イラガはカキなどの落葉樹を食害するものとばかり思っていましたがヒロヘリイラガはシラカシ等の常緑樹も食害します。新横浜公園でもシラカシ、サクラ、カエデを食害しています。食べ方も葉脈を残し葉を透かすような食べ方をしますからすぐわかります。そのような葉を見たら要注意です。イラガはチャドクガと並んで有毒害虫と呼ばれています。その理由は刺されるととても痛いからです。駆除方法は早期に発見して毛虫の付いている葉をとってしまうことです。早い時期だと1枚の葉に小さな幼虫が群生しているので効率的です。
大きくなった毛虫は叩き落とします。落とされた毛虫に樹を登る力はありません。イラガの足は地面を歩くようには出来ていないのです。ほっておいても死んでしまいます。
※現在はきちんと駆除しています。