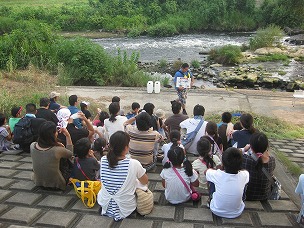芝生観察日記の第五十三話です。
平成25年8月23日(金)
日産スタジアムが開場して初めてとなる3週連続のコンサートが終わりました。8月4日のももいろクローバーZコンサートでは、芝生内にアリーナ席を設けない会場レイアウトだったため芝生へのダメージはありませんでした。サザンオールスターズの際には、前回ご紹介した通り、初めての試みで使用した芝生保護材の効果により39℃を超える猛暑の中でも芝生のダメージは比較的軽くて済みました。
そして、17日、18日の両日に亘って開催された東方神起のコンサート。気温自体はサザンの時より3~4℃低めでしたが、35℃に迫る厳しい猛暑の中、今回は全国のスタジアムコンサートで一般的に使用されているテラプラスという芝生保護材を使用しました。
元々、芝生をアリーナ席として使うコンサートの場合、どこのスタジアムも芝種や環境の違いはあるものの、芝生にはそれなりに大きなストレスがかかり、最悪の場合は張替えのリスクも覚悟して開催判断をします。
下の写真は、サザンオールスターズと東方神起の後の芝生の定点比較です。
8/12 コンサート前の状況 及び コーナー付近を上から撮った状況


8/19 コンサート後の状況 及び コーナー付近を上から撮った状況


いかがでしょう。芝生の痛みが伝わるでしょうか。芝生保護材の違いは芝生に与える影響の一因としてありますが、それに加えて今回は2週連続で芝生にストレスがかかったことでダメージが嵩みました。
また、今回テラプラスを撤去して驚いたことは円形の足型部分の葉が赤く焼けていたことです。
通常、コンサートが終わって2、3日経過した後でこのように赤くなることは想定される状況でしたが、今回は夜中に撤去したその段階で赤く焼けていた状況は初めての経験です。それだけテラプラス内が熱かったのだろうと推察できます。確かに8月に入ってずっと30℃を超える厳しい暑さが続いており、夜間温度も下がらない状況で敷設したテラプラス内は50℃を超えていたに違いありません。
コンサートとコンサートの狭間の芝生管理作業も想ったようにできなかったことや天候など色々な要因が積み重なって想定よりも芝生に重いダメージが残りました。
夏場のコンサートにおいては、芝生保護材を被せることで日照阻害や蒸れによる過湿障害、保護材接地面の踏圧障害などが芝生にダメージを残します。また、これに加えて我々が計算しきれないものとして、冬芝(ライグラス)の衰退による裸地化です。
下の写真は、南側のゴール前の状況です。ゴール前は、そもそも混戦で激しく荒れる場所なので芝生自体の状態も決して良好ではなく、大きな大会前などに適宜張替えを行うことがあります。そのため、張替えを行った場所とそうでない場所では芝生の根の下り方にも差があり、激しい利用が続くとその根の差が利用に対するストレス耐性となって正直に現れます。
コンサート後アウェー側ゴール前の状況 と 写真の近景状況


上記、ゴール前の張替え状況 と 張替え後の状況


土の中に深くまで根を下した周りの芝生は、芝生保護材を撤去した後の回復状況がある程度想定できますが、一度張替えた箇所は根が短く、同じストレスを受けた際のダメージの度合いが想定し辛いのです。そのため、芝生保護材を剥がしてみてビックリというケースが良くあります。
今回は、正にそんなケースの最たる状況で、上の写真は芝生保護材を被せた結果、ライグラスが枯れて衰退し、裸地となった場所の張替え前後の写真です。
気が重い3週間を振り返ってみると、今年の猛暑の中でライグラスがここまで残ってしまっていることは想定外であり、コンサートを迎える前までに全面ティフトンに切り替わってくれていれば張替えの必要はなかったという悔しさが残ります。
年々、地球温暖化のせいか四季の変化が著しい天候になっている気がします。それに伴い、芝生の管理も先が読めない難しさを感じています。
今回のコンサートでは、写真のような裸地がフィールドの所どころに点在してしまいました。首位となったF・マリノスの大事なホームゲームを1週間後に控えて、芝生の生命力に期待する一方で我々もできる限りの策を講じていきます。
競技場の芝生として本来の使い方に支障を来しては本末転倒ですから。
芝生観察日記の第五十二話です。
平成25年8月12日(月)
サザンオールスターズ「SUPER SUMMER LIVE2013 灼熱のマンピー!!G★スポット・解禁!!」 連日38℃を超えるまさに灼熱の二日間が終わりました。フーッ。。。
さて、2週連続のコンサートによる芝生のダメージを少しでも緩和させるために初めて使用する芝生保護材で挑んだ結果をご報告します。
8/10 コンサート前の状況 及び コーナー付近を上から撮った状況


8/12 コンサート後の状況 及び コーナー付近を上から撮った状況


さて、どうでしょう。コンサート前後の比較ですが、写真ではダメージの状況が解らないと思います。かえってコンサート前の方が色合い的に悪そうですね。今回の結果、速報としてはこれまで使ってきた保護材よりも芝生自体のダメージは小さかったと見ています。サッカーであれば今週末には、できそうなダメージレベルですが、コンサートのダメージは3日後辺りにガクっと落ち込む事が多いので、予断は許せません。しかし、大きなチャレンジでしたが、ひとまず安心できる結果となりホッとしています。
今回は、主催者さんを始め多くの方のご協力もあって新しい保護材の導入に至りましたが、今回の結果を色々な視点で検証し、今後行われるコンサート時の芝生保護に活かしていきたいと考えています。
ちなみに、今週末に開催が予定されているコンサートでは、従来の「テラプラス」を使用する予定です。限られた時間を使って今回のダメージを少しでも和らげて臨みたいと思います。
ではまた、今週末の状況をご報告します。
芝生観察日記の第五十一話です。
平成25年8月10日(土)
芝生観察日記の更新を楽しみにされていた皆さまお久しぶりです。
8カ月ぶりの更新となってしまいました。
ようやく夏真っ盛りとなって汗ばむ陽気が続いていますが、例年より10日も早く梅雨入りしたものの雨量は少なく、戻り梅雨があったり、曇天日が多い天気の影響で冬芝から夏芝へのトラジションが遅れ気味な今年の日産スタジアムの芝生コンディションです。
全国的に見ると記録的な大雨に見舞われている地域もあり、異常気象という言葉で逃げたくはありませんが、芝生に限らず植物管理をされている方にとっては悩ましい問題ではないでしょうか。
Jリーグは中盤に差し掛かろうとしていますが、ホームのF・マリノスは開幕から好調を維持して現在2位。ACLの出場権どころか優勝の二文字が浮かぶ活躍なので芝生を管理する我々グリーンキーパーにとってもやり甲斐のある毎日です。
が、さて、好調が故に気になる芝生の状態。。。
初めて6月に開催したコンサート。多くのお客様にご来場いただきTV等でも放映され、普段は日産スタジアムの名前を聞いた事がない方にも知っていただけたイベントでした。開催が1日ということと、梅雨入り前後という時期もあって芝生のダメージは小さいと考えていましたが、曇天日の多かった梅雨時季の日照不足が響いて、想定外に芝生が落ち込み回復に時間を要しました。
しかし、ここへ来て猛暑となり夏芝のティフトンがようやく元気になってきました。このまま一気にトラジションを完了させたいところですが、今週と来週の2週に亘ってコンサートが開催されます。
スタジアムの運営上は、ありがたいイベントですが芝生を管理する我々にとっては胃の痛い夏がやってきました。
コンサートでは芝生フィールドも「テラプラス」という芝生専用の保護材を設置してアリーナ席となります。芝生専用とはいえ芝生は傷みます。しかも2週連続ではさすがに芝生も辛いのです。
マリノス、そして日本代表のホームとして常に最高の状態をというのが我々のプライドです。コンサートの後だから仕方ないよねとは言われたくないので、コンサートをしても芝生が傷まない保護材を研究して辿りついたのが写真の通称「はるさめ」。正式名称は「コアマット」。芝生の保護材ではなく、浸食防止マットが本来の用途です。芝生の保護材として採用したのが新潟の東北電力ビッグスワンスタジアム。このマットを保護材として使った際の特許も取得しています。上には上がいるものですね。


今回は、このマットを新潟からお借りし、我々が試験してコンサート時の芝生保護材として新しい可能性を模索した結果、探し当てたのがイベント用床面養生材「ポーターフロア」。


コアマットの良さは前から知っていましたが、これだけでは大事な芝生を守ることができないので別の資材との組み合わせが必要です。色々と試験を重ねた結果「コアマット+ポーターフロア」の組み合わせであれば2週連続のコンサートを開催しても何とか8月29日のJリーグ浦和戦、そして9月10日に控えた日本代表戦にホームとして恥ずかしくない芝生に回復させられると信じてサザンオールスターズのコンサートでデビューします。日本、いや世界初のチャレンジです。
2002年ワールドカップの会場でもあるビッグスワンスタジアムとのコラボでもあり、非常に結果が楽しみです。

サザンオールスターズ35周年記念の復活コンサート。スタジアム内は満員のお客様で盛り上ってます。
結果は、週明けに報告します。

★写真:ナミアゲハ
撮影日:平成25年8月7日
暑い日が続き、夕立も時々降る夏らしい陽気が続いています。
雨や公園内の散水によってできた水たまりにナミアゲハが来ていました。ナミアゲハは、アゲハチョウの代表種で、幼虫はミカンなどの柑橘類の葉を食べます。キアゲハにも似ていますが、前羽の模様が少し違い、キアゲハよりも全体的に黒い特徴があります。チョウは蜜を吸うために花に集まりますが、今回のように水たまりで水を飲む姿もよく見られます。
昆虫も熱中症になるかはわかりませんが、暑い日には水分をよく取り、熱中症にならないように気をつけましょう。